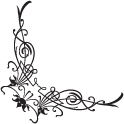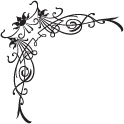この列車に乗ったときから、なんとなく注目されているのは気付いていた。
(……これが、女性として初めて王国特殊調停官となった私に対する羨望のざわめきだったらいいのだけれど)
そうではないことはそろそろ分かっている。注目されているのはアーシャではない。アーシャの隣にいる従者で事務補佐官のオーディンの方だ。
「どうにも騒がしいですね。やはり、短距離とはいえ個室を取った方がよろしかったでしょうか。アーシャお嬢様」
オーディンは周囲の様子を気ぜわしそうに見ている。列車内にはどこかの寄宿学校から里帰りする生徒なのだろうか、若い娘が多く乗っていた。
オーディンは輝く金色の髪に、穏やかさと強さを兼ね備えたような凜とした琥珀色の瞳を持っている。街を歩いたら十人中十人が『あの美丈夫はどこの貴族様だ?』と振り向くこと請け合いである。そんな中で彼の横にいる、周囲から屈辱的にも『ちびっこいお嬢ちゃん』と称されてしまう侯爵令嬢のアーシャになど誰も目もくれない。残念だが、事実なので仕方がないため、もう気にしないようにしている。
地方での仕事を終え、司法庁がある王都へと戻る途中だった。近距離のため馬車という選択肢もあったのだが、行きは列車で来たため、列車で帰ろうということになったのだ。しかし、この列車の混雑ぶりを考えて馬車を使ったほうがよかったかもしれない。
「この混み具合からして、きっと個室もいっぱいよ。別にいいわ、このボックス席で充分よ」
「アーシャ様が望んでいると言えば、用意させることは可能かと存じますが?」
というより、俺が言うことを聞かせますが、というように聞こえる。いや、彼は基本的に平和主義者なので車掌となんとか交渉して個室を取れるようにするのだろうが、そのためにもしかして個室から追い出される人がいるかもしれない。それは気の毒だ。
「本当に大丈夫よ。今から個室へ移動する方が疲れるわ。ほんの少しの時間ですもの」
「ですが、こんなに込み入った列車の中です。アーシャお嬢様に対したよからぬ企みをする者がいるかもしれません」
オーディンは油断ない目つきで周囲を見つめる。
確かにアーシャは侯爵令嬢であり、普段はお供の侍女をふたりに従者をひとり連れているくらいが普通ではあったが、ここはボックス席とはいえ一等客室である。そんな危険はないように思える。
(オーディンのことを見て囁きあっているのも年若いお嬢さんたちだし)
とてもそんな危険があるような雰囲気ではない。むしろ、オーディンの方が危険があるのではないか……年若いお嬢さんたちに周りを囲まれて質問攻めにあい列車から降り損なうとか、と考えてしまうくらいだ。
「ええっと……大丈夫よ、なにしろオーディンが側に居てくれるんだから」
するとオーディンはぱあっと顔を輝かせて任せてくださいとばかりに胸を張った。
「それはそうです! 俺がいればなんの心配もありません! 身を挺してお嬢様をお守りいたします」
「……頼もしいわ。お願いね、オーディン」
彼の暑苦しいくらいのやる気の見せように、少々呆れたように言ったのにオーディンはそんなものまるで気にする様子はない。
そんなやりとりをしているうちに、先ほどまでひそひそと話していた娘たちのうちふたりがやって来て『あなたが話しかけてよ』『いえ、あなたが』というやりとりを始めた。オーディンを従者にしていると、こんなやりとりを見るのも慣れたものだ。
「どうかしたの?」
そうして、もう早くしてよとばかりに話を促すのはアーシャの仕事だ。娘たちは照れてなかなかオーディンに話しかけられないから。
「あの……そちらの方と、少しお話がしたいのですが」
彼女たちは俯いて、オーディンの顔も見られないような有様である。それに対してオーディンは、
「お嬢様は大切なお仕事を終えられてお疲れなのだ。向こうに行ってくれないか」
そんな素っ気ない言いようである。普段は誰に対しても優しいオーディンであるが、このような場面ではアーシャを気遣ってアーシャのことを優先させる。
娘たちは戸惑った表情を見せつつ、しかしすぐにその場からは離れずにオーディンのことを見つめていた。自分からもなにか言った方がいいだろうか、とアーシャが迷っていたとき、その娘たちの間から身なりの整った紳士が声を掛けてきた。娘たちは道を空けるように後方へとよける。
「その制服に階級章は……あの、もしやあなたは、王国特殊調停官様ではないですか?」
「えぇ? 王国特殊調停官ですって」
「やだ! なにそれカッコいい……!」
それを聞きつけた娘たちがきゃーきゃー言い始めた。
(えっと……王国特殊調停官は私で、オーディンはその事務補佐官なんだけれどね!)
しかし、その勘違いには既に慣れていた。任務地でもオーディンの方が王立特殊調停官と勘違いされることが多いからだ。
王国特殊調停官、別名『貴族のケンカ仲裁係』。貴族同士が争って裁判になり両者の家名に傷がつくようなことになってはいけないので、その前に話し合いで解決しようと努める役割を持っている。仲裁、とはいうが、調停官に争いをおさめる強制力はなく、両者納得がいくように話し合いの手伝いをするというのが主な仕事である。
「ええ、そうですが。それがなにか?」
アーシャはツンと澄ました表情でそう言う。王国特殊調停官はまだまだ世間での馴染みが薄く、こうして声を掛けられることは稀である。ちょっと偉そうな態度をしてみたかったのだ。
「女性の調停官が誕生したとは聞き及んでいましたが、まさかこんなところでお会いできるとは。握手をしていただいてもよろしいですか?」
「ええ、もちろん」
アーシャは紳士の申し出に気持ちよく応えて彼と握手をした。
そうそう、こういう扱いを待っていたのだと気持ちが盛り上がった。人々から尊敬と羨望を受けるような職業なのだ、王国特殊調停官というのは。
「君たちは学生かね?」
紳士が問うと、オーディンを見に来ていた娘たちは小さく頷いた。
「君たちも勉学に励み、彼女のようになるといい。これからは女性も仕事を持つ時代だ」
そう言って、アーシャに会釈をしてからその場から立ち去った。娘達は顔を顔を見合わせつつ、
「そうね、こんなイケメンを従者にできるなら、目指してみてもいいかも!」
ああ、そういうことでは全然ないのにと酷くがっかりしてしまった。
王国特殊調停官をこんなお嬢様方にも知られる存在にならなければならない。そのためにはもっと励まなければならない。
「……でも、もうちょっと憧れられる存在になってもいいのにな」
しかし、ついついそう言葉が漏れてしまった。それが失敗だった。
突然、オーディンがすっと立ち上がり娘の前へと立った。なにを、と思って怪訝な表情を向けると、彼は『お任せください、お嬢様』とばかりにアーシャに向かってぐっと親指を突き出し、それから再び娘たちの方を向く。
「王国特殊調停官を知らないなんて、不勉強だ。俺が教えてやろう」
オーディンがそう言うと、近くにいたふたりの娘たちだけではなく、周りからわっと娘たちが集まってきた。
いや、娘たちだけではない、ご婦人や、年かさを増した男性たちも立ち上がり、あるいは座席に座ったままでオーディンへと視線を向けた。
「そもそも、王国特殊調停官は司法庁に所属しており、難しい試験を突破できなければなれない職業である」
オーディンの声は涼やかでよく通り、言葉のひとつひとつがはっきりとしていてとても聞きやすい。人々から好まれる語り口なのである。今まで興味がなさそうにしていた人達までオーディンへと視線を向けた。
「ここにいらっしゃるアーシャお嬢様はその王国特殊調停官の試験を、女性として初めて、しかも最年少で通られた素晴らしい方なのです!」
「おお~~」
周囲の視線が一斉にアーシャへと集まる。
皆にもっと注目されたい、なんて思っていたのにいざそんな状況になると照れて顔を背けたくなってしまう。しかし、ここは王国特殊調停官として毅然とした態度を取らないといけない、と満足げな表情を作って頷いておいた。
「しかもその初仕事において大手柄を挙げて、なんとあの司法庁長官から直々にお褒めの言葉を賜ったくらい優秀な調停官なのである!」
「おお~~」
更に大きなどよめきが生まれ、驚きと羨望の視線がアーシャへと注がれる。だんだん、表情を作っているのも辛くなっていった。
「思えば、アーシャ様は幼少のみぎりから特別優秀な方だった。王立大学卒業の家庭教師がもうアーシャ様に教えることなどなにもないと言って家庭教師を辞めてしまったくらいなのだ。旦那様の書斎にある本は八歳の時に全て読み終えてしまったし、辞書の中に誤字を見つけて出版社に手紙を出したくらいだ」
「おおぉ~」
車両の中に大きなどよめきが生まれる。
それが車両の外にまで響いたのか、隣の車両から車掌がやって来た。ああ、きっと車掌が『車内ではお静かに』とでもなんとでも言ってオーディンの言葉を止めてくれるだろうと期待したのだが、
「お嬢様は生まれつきとても頭がいいが、それだけではない、なによりも努力を惜しまないお方だ。王国特殊調停官の試験に挑まれるのに、夜中勉強をして体を壊されたくらいだ。そんなに根を詰めなくともきっと合格できるだろうという旦那様の言葉に首を振り『いえ、上には上がいるのです。どんなに努力しても努力し過ぎということはありません』とおしゃられて。なんと謙虚なお方か! その結果、見事試験に合格し、女性初の王国特殊調停官という栄誉を勝ち取ったのだ」
最初は怪訝な顔をしていた車掌なのに、腕を組み、オーディンの言葉に大きく頷いている。……どうやらもう救いはないようだ。
「しかもお嬢様はとてもお優しい。屋敷中の使用人の名前を全て覚え、しかも誕生日まで全て把握し、特別な贈り物をしてくださるのだ。こんなに素晴らしいお嬢様が他にいるだろうか! 否! アーシャお嬢様以上の方などこの国……いや、この世界にいるはずがない」
オーディンの言葉がだんだん演説めいてきた。車両内の誰もが彼の言葉に耳を傾けているのをいいことに彼の声はどんどん大きくなり、そして熱を帯びてくる。それに伴って、聴衆たちが彼の言葉にどんどんのめり込んでいるのが分かる。
「……見た目によらず素晴らしい方だったのね」
「ほら、能ある鷹は爪を隠すというし……それを体現されているような方なのだわ」
「さすが、こんなイケメンが仕えているだけあるわ」
娘たちのささやき声が聞こえてきて、アーシャは恥ずかしくて耳を塞ぎたくなった。
(やめて……! もうやめて!)
皆から尊敬を集めたい。
望んだことのはずなのに漂うコレジャナイ感に苛まれながら、アーシャは早く列車が王都に着かないかなと願っていた。
番犬従者と令嬢調停官 あなたのケンカ、仲裁いたします!/伊月十和